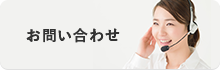よくあるご質問:環境緑化分野
芝生の種類の選択について
-
一般的に学校の校庭の土壌は表面処理(塩化カルシウム)による表面固結やクレーなど固く締まった土壌を用いている場合が多いです。そのままでの土壌を芝生化は難しい場合があります。土壌分析や試験施工などを部分的に行ってから全面を芝生化することをおすすめします。透水性や排水性の改良(暗渠排水)、水たまり部の補修、適正な土壌への置換など物理的な処置と土壌のpHや成分など化学性の改良も必要となり、大掛かりになる可能性がありますので、専門業者に調査を依頼するのが望ましいです。芝生に適する土壌条件を確保した上で、用途や利用頻度によって芝生の種類を設定します。仙台地域ですと寒地型芝生と暖地型芝生の両方が可能な地域ですが、最近の気象変動により温暖化(猛暑)の影響もありますので造成後の管理設備も考慮しながらご検討ください。一般的には利用頻度が少ない場合は省力管理のノシバ(張芝)を、利用頻度が多い場合は生育が旺盛なケンタッキーブルーグラスを主体とした寒地型芝品種の混合か暖地型芝生のバミューダグラス(栄養繁殖系)をおすすめします。
-
一般地や西南暖地では暖地型芝草のバミューダグラスとセンチピードグラスがおすすめです。また高寒冷地ではクリーピングレッドフェスクやチューイングフェスクなどの細葉ファインフェスク類が荒れ地には向いていますが、これらは踏圧に弱いためケンタッキーブルーグラスやトールフェスク、ペレニアルライグラスなど数種類の混合がおすすめです。
-
太陽光発電パネル下にはシロクローバが多く用いられています。その他に高寒冷地ではベントグラスやケンタッキーブルーグラス、一般地や西南暖地ではセンチピードグラスやバミューダグラスが適しています。生育初期に雑草が繁茂しないよう管理(手取りや刈取り、選択性除草剤等)などをしっかり行い、密度を高めて地表面を露出させないようにすると草木が侵入しづらい状態になります。また、播種前の状態が既に雑草が生育している場合は、除草剤等での前処理もご検討ください。
-
一年中、芝生を緑にするためには、2つの方法があります。1つ目の方法は、寒地型芝草を利用する方法です。ただし関東地方以西の夏期に高温となる地域では、耐暑性品種を用いても夏枯れする事があります。夏期の散水と殺菌剤散布が必要になりますのでご注意ください。2つ目の方法は、暖地型芝草をベースとし、ウィンターオーバーシーディングを行う方法です。ティフトンシバやバミューダグラスなどの暖地型芝草は、良好に越夏しますが、冬期に休眠して褐色化します。このため、毎年秋期にペレニアルライグラスやアニュアルライグラス等の寒地型芝草を追播します(ウィンターオーバーシーディング)。翌年、気温が上昇するとライグラス類が衰退し、ティフトンシバやバミューダグラスなどの暖地型芝草に切り替わります。関東地方以西の多くのサッカー場では、この方法によって、一年中、緑の芝生が維持されています。
-
芝草は、日当たりを好む植物です。多くの芝草の種類の中でも、寒地型芝草であればフェスク類、暖地型芝草であればセントオーガスチングラスやセンチピードグラスが、比較的日陰に強い芝草とされています。しかし、1日の日照時間が4時間より少ない場合は、どの芝草でも良好に育てることは困難です。そのため周辺の樹木を剪定するなど、できるだけ日当たりが改善されるようにします。なお寒地型芝草であればトールフェスクを主体にした混合をおすすめします。
-
種子繁殖系バミューダグラスを利用する場合は、芝生になるまで時間が掛かりますが、比較して安価な費用で芝生が作れます。一方、栄養繁殖系は、切り芝(ソッド)、ポット苗、ストロン苗が流通しており、種子繁殖系品種の利用に比べて短期間で芝生が作れますが、施工費用が高くなってしまいます。芝生の質を比べると、栄養繁殖系の品種の方が若干密度が高くなりますが、それ程大きな違いではありません。なお、いずれの利用の場合でも、密度が薄くなったときは種子繁殖系品種の追播で補修が可能です。
-
これらの芝草は、匍匐茎によって繁殖する栄養繁殖のため、種子ができません。このため、切り芝(ソッド)やストロン苗で流通しています。なお、栄養繁殖系バミューダグラス品種の代替として、形態や特性も類似している種子繁殖系バミューダグラスの品種をご利用ください。
-
芝草の多くは、耐虫性や耐暑性を向上させる「エンドファイト」と言う内生菌が共生しています。エンドファイトは家畜毒性を持つ種類もあるため、ペットや動物に与えることができません。ペット等の餌としての利用は、ペットショップ等で販売されているペット用スプラウト(通称:猫の草)をおすすめします。
-
芝生として販売している品種は、特定外来生物に指定されているものはありません。外来生物法に基づく「特定外来生物」は、植物ではオオキンケイギクやオオハンゴンソウなど19種が指定されており、保管や栽培が禁止されていますが、芝生の多くは生態系被害防止外来種リストの「産業管理外来種」に指定されており、「適切な管理が必要な産業上重要な外来種」とされています。なお佐賀県では、条例でトールフェスクの栽培が禁止されていますので、ご注意ください。
芝生の播種時期・播種方法について
-
播種作業は、天候の良いとき(晴れまたは曇り。種子が飛ばされないように風の少ない日や時間帯を選ぶ。)をおすすめします。播種前の準備としては、床土(砂)には必要に応じて土壌改良資材を利用し、透水性・排水性を改善し、pHを6~7に調整してください。表土(表面)は整地し、元肥として化成肥料を50g/㎡を均一に散布しレーキ目を付けます。
種子は、回転式や落下式の播種機を使用して播種します。播きムラが病気の発生源となります。均一に播くことが最も重要ですので、種子を等分して、タテ、ヨコ、斜めの「3方向播き」を行うと均一に播種することができます。
種子と表土がなじむように、レーキなどを用いて軽く覆土します。その後よく鎮圧し、種子が動かないように優しく散水します。その後は発芽するまで適宜散水し、発芽が揃い後5cm程度伸びた時点で手取り除草をしっかり行います。 -
当社では、種子を適切な条件下で保管しておりますが、出来るだけ種播き予定日に近い日に使用する数量を購入し、使い切ることをおすすめします。もし、種播き後に種子が余った場合は、密封し冷暗所に保管する事をおすすめしますが、発芽率が低下していくことをご理解いただき、できるだけ早めのご使用をお願いいたします。
芝生の種子の発芽について
-
発芽には「水」「温度」「土壌条件」「購入後の種子保管」等の要因が影響します。「播種時期」が適期(温度が関係)では無い時期に種子を播種しても発芽はしません。また、播種時の土壌水分が無くその後も雨がほとんど降らない場合にもは、種子が水分を吸水できず発芽はしません。更には、土壌のpHや何らかの成分が過剰な状態、豪雨後の停滞水の継続等(排水性不良)の場合も、発芽しない場合があります。利用する品種の適期に播種、播種後の散水(種子が流れない程度に散水、天候を見ながらの散水等)を行ってください。また、播種前の土壌改良が必要な場合は資材等の利用により改善することをおすすめします。
条件が整えば、ケンタッキーブルーグラスやバミューダグラスは10日~2週間で発芽が開始されます。またウィンターオーバーシードの場合は、低温期となるため発芽まで2週間以上を要する場合もあります。
以下は、考えられる発芽不良の原因です。
●高温多湿なところに、種子を保管していた。
●播種する土壌を、硬めに締め固めた。
●排水が不良で、しばらく水溜りができていた。
●冬期など、播種適期ではない時期に播種した。
●播種後に雨が降っていない。散水も行っていない。
●播種後、目土を厚く掛けすぎた。
●播種後、種子が風に飛ばされた。 種子が雨に流された。 種子が鳥に食べられた。
●オーバーシードの場合、ベースの芝のサッチを十分取り除かなかった。または短く刈込まなかった。そのため種子が床土に到達できず、発芽が不良となった。 -
発芽直後の芝草は、非常に小さいため、発芽直後に衰退してしまうことがあります。以下、発芽直後に起こりやすい芝生が衰退する原因です。
●根が浅い時期に乾燥し、枯死した。
●排水が不良で、病害に罹病した。
●発芽直後に、鳥や害虫に食べられた。
●日陰地に種子を播いた。
●発芽後、直ぐに芝生を利用し、踏圧を掛けた。
●発芽後、一気に低く刈り込んだ。
●肥料を大量に散布した。または肥料散布後に芝生に立ち入った(肥料焼け)。
●雑草が大量に発生し、日陰となり、衰退した。
芝生の更新方法について
-
ウインターオーバーシードとは、1年で2種類の芝を使い分けて、一年中緑の芝生を維持する方法です。暖地型芝生は気温の下がる10月頃から色あせが始まり、やがて休眠状態となり、春まで緑度が失われ枯れた状態になります。この晩秋から春までの時期に芝生地の緑度保持のために秋に専用の寒地型芝生の種子を播種して、徐々に寒地型芝生に切り替えていきます。また、春の気温の上昇とともに、暖地型芝生は休眠から覚めて生育を開始し初夏には暖地型芝生に切り替わります。なお、ベースとなる芝草は夏の生育旺盛で傷みからの回復が早い暖地型芝生(バミューダグラス等)を選定しウィンターオーバーシードに使用する寒地型芝生は、一年生で特に耐暑性が低く、春期のの衰退が早いライグラス類の品種の選定が必要です。
-
4月初旬から6月中旬がトランジッションの時期となります。冬芝の生育を抑えるために施肥を停止し、刈込のみ継続します。気温が高まり、夏芝(ベース芝)の生育が始まる頃より低刈をし始め、地表に日光が当たりやすい条件を作ります。夏芝が冬芝の間から確認できるようになりましたら、窒素成分で5g/㎡以上を追肥し、たっぷりと散水します。乾かないよう適宜散水をし、夏芝の萌芽を促します。梅雨明けには気温が急激に上がるため、夏芝の勢いが高まると共に冬芝の生育が弱まり、この頃から通常の夏芝管理に切り替えます。梅雨中に低温が続き切り替わりが悪い場合は選択性の除草剤による冬芝の除草をおすすめします。
-
完全に作り直すためには、コウライシバを剥がし(または除草剤で枯らし)、床を耕起、整地しなおして、ティフトンシバの苗を植付けます。一方、簡易的な方法として、コウライシバにティフトンシバの苗を植付け、2~3年かけて、徐々にティフトンシバに切替えていくことも可能です。コウライシバベースでウィンターオーバーシーディングを行い、春期にコウライシバが傷んだ部分に、ティフトンシバの苗を補植することで、徐々に切り替えていきます。
芝生の管理方法について
-
ケンタッキーブルーグラスやバミューダグラスでは15mm程度、ベントグラスでは4~5mm程度まで低刈が可能です。低刈りする場合、一度に半分以上の草丈に刈込むと、茎だけの状態(軸刈り)となり、大きなダメージが生じます。このため葉を残す程度に、徐々に刈高を下げて行く必要があります。また、低刈りする場合は、土壌の表面の起伏が少ない事が条件となります。
-
芝生はイネ科の植物ですが、発芽直後は見分けしづらいので、葉が数枚展開した際の時期が見分けやすくなります。このため、以下に簡単な見分け方を説明します。
●トールフェスク:葉脈が何本もあり、葉が硬く、ザラザラしています。
●ケンタッキーブルーグラス:葉脈が1本で、葉の先端がボートの舳先状になります。
●ライグラス:葉の裏側に光沢があり、茎の根元が赤くなります。
●チューイングフェスク:葉が針のように細い特徴があります。
○メヒシバ(雑草):葉が丸く太い特徴があります。https://wssj.jp/kaisetsu/24_mehish/mehish_top.html
○スズメノカタビラ(雑草):葉や茎が淡く穂をつけます。https://wssj.jp/kaisetsu/14_suzumk/suzumk_top.html -
芝草が罹病する病害は、土壌病害と茎葉病害に大きく分かれます。排水不良時に根が腐るピシウム病(土壌病害)には、タチガレン液剤がおすすめです。また芝生表面に円形の病斑が生じるブラウンパッチ(茎葉病害)には、ヘリテージ顆粒水和剤やグラステン水和剤がおすすめです。詳しい施用方法や適用作物などは、農薬の販売店等にご相談ください。
-
土壌中に、コガネムシやヨトウムシなどの幼虫が潜んでいる可能性があります。幼虫の密度が増えると、芝生の根が切断され、枯れてしまうことがあります。状況に応じ、スミチオン乳剤、オルトラン水和剤などの殺虫剤を散布します。なお詳しい施用方法や適用作物などは、農薬の販売店等にご相談ください。
-
寒地型芝草は、暖地型芝草に比べ、暑さに弱い特性があります。最近は寒地型芝草の中でも耐暑性が高い品種も育成され、関東以西でも越夏できるようになりましたが、高度な管理が必要となります。根まで枯れてしまった場合は、回復が見込めません。そのため、再度播種または張替えが必要になります。夏枯れの程度が低い場合には、秋期に回復することもあります。この場合、部分的に追播することをおすすめいたします。レーキなどを利用して芝草の残渣を取除き、種子を播き、目土を1~2mm散布し、鎮圧します。
以下は、寒地型芝草を夏期に枯らさないポイントです。
●耐暑性が高い品種を選ぶ。
●生育が旺盛な時期は、適切な芝刈り、施肥(液肥散布も含め)を行う。
●高温期は、病虫害が多発する時期になるため、定期的な薬剤散布を行う。
●乾燥対策として、日中を避け、早朝に十分に散水する。なお日中の高温な時間帯は、表面温度を下げる目的で、霧状に噴霧することが効果的。
●排水不良は、根腐れや病害発生の原因となるため、予め芝生表面に勾配をつけたり、定期的な更新作業(穴あけや目土散布など)を行ったりする。 -
肥料が少ない場合、冬期に葉が黄色くなることがあります。ウィンターオーバーシードの種播き後、12月までに粒状肥料をしっかり施肥し、十分に育てておく必要があります。厳冬期は粒状肥料を散布しても効きづらいため、アミノ酸や糖を含む液肥を散布します。また寒冷紗など被覆資材でカバーするのも効果的ですが、蒸れないように注意が必要です。
-
コウライシバ、セントオーガスチングラスなどの芝草は、種子の流通がありません。補修の規模が小さい場合は、芝生の外周部から生育の良い匍匐茎を切り取って、植え付けます。面積が大きい場合は、新たに切り芝(ソッド)を購入するか、外周部の芝生を切り取って植え替えます。なおこれらの芝草は、匍匐茎によって繁殖する栄養繁殖のため、施肥を行えば復活していきます。